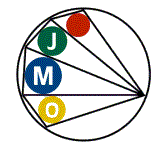公益財団法人 数学オリンピック財団について
当財団は、公益財団法人 数学オリンピック財団(The Mathematical Olympiad Foundation of Japan:JMO)と称し、内閣府所管の公益財団法人です。当財団では、「国際数学オリンピック(The International Mathematical Olympiad:IMO)」、「アジア太平洋数学オリンピック(Asian Pacific Mathematics Olympiad:APMO)」および、これらと関連する国際的な数学の競技会への参加者の選抜・派遣等に係る事業を行うとともに、その成果を踏まえ広く高等学校および中学校等における数学教育に関する調査研究、普及啓発等の事業を行い、我国の数学および数学教育の振興並びに青少年の健全育成に寄与することを目的としています。
IMO を始めとする数学の競技会の目的は、「全ての国の数学的才能に恵まれた若者を見出し、その才能を伸ばす手助けをし、若者達と教育関係者が互いに民間レベルでの国際交流を深め,教材等の情報交換を行うこと」です。
日本における IMO への派遣事業は、1988年にオーストラリアの首相から日本の外務省と文部省(当時)に、大会への日本参加要請文が送付されてきたことがきっかけとなりました。 1989年、当財団前身の「国際数学オリンピック日本委員会 (The Japanese Committee for International Mathematical Olympiad:JCIMO ) 」の委員2名が、第30回 IMO 西ドイツ(当時)大会を視察し、翌年の第31回 IMO 北京大会に、文部省(当時)か らの支援と多くの数学者からの寄附金により、日本は初めて IMO に参加しました。 その後、協栄生命保険株式会社(当時)名誉会長・川井三郎氏のご尽力により、川井氏個人の多額の寄付に加え、協栄生命保険株式会社、富士通株式会社、アイネス株式会社等の各企業からの多額のご寄付を基金として、1991年3月20日に文部省(当時)所管の「財団法人数学オリンピック財団」が設立されました。
2013年4月1日からは、新しい公益法人制度が施行されたことを受け、数学オリンピック財団は、より一層の社会的信頼を得るべく、公益財団法人として新たにスタートしました。
公益財団法人 数学オリンピック財団 の主な事業内容
当財団では、上記の目的を達成するために、現在、主に次の事業を行っています。- 1 「日本数学オリンピック(JMO)」の開催(毎年11〜3月)
- 2 「日本女子数学オリンピック(JGMO)」の開催(毎年11〜1月)
- 3 「日本ジュニア数学オリンピック(JJMO)」の開催(毎年11〜3月)
- 4 「国際数学オリンピック(IMO)」への日本選手団派遣(毎年7月)
- 5 アジア太平洋数学オリンピック(APMO)の実施(毎年3月)
- 6 「ヨーロッパ女子数学オリンピック(EGMO)」への日本選手団派遣(毎年4月)
- 7 数学オリンピックに関する教材の開発など
- 8 数学、特に数学オリンピックに必要な知識の普及活動
理事長ご挨拶
理事長ご挨拶数学オリンピック財団 沿革
数学オリンピック財団 沿革数学オリンピック財団 定款
数学オリンピック財団 定款【改訂履歴】
〇2022(令和4)年6月5日改訂
〇2020(令和2)年6月7日改訂
〇2019(令和1)年4月23日改訂